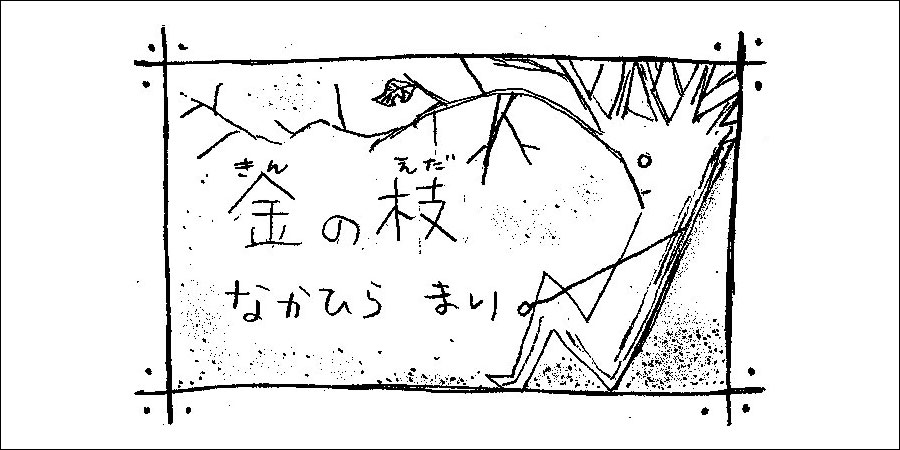『理趣経』によると、密教の教典には、興味深い点がほかにもたくさんある。わたしが興味を引かれたのは、お経に登場するキャラクターについて。
松長氏の解説によると、説法をするのは本来、釈迦(しゃか)のはずだが、理趣経や大日経、金剛頂経など、中期密教の教典は、大日如来(だいにちにょらい)の教え、ということになっているそうだ。つまり、実在の人物であった釈迦ではなく、大日如来という架空のキャラクターが教えを説いているのだという。
大日如来は、その名の通り、日の光のように絶対的な真理という意味。それは、他に比べて完全というように相対的なものではなく、絶対的な真理ということだ。(太陽はこうした概念の象徴になることが多い。神道の天照大神も同じような意味だろう。)すると大日如来は、真理そのものなのだから、自分でものを語らないはずだ。正確には、釈迦が大日如来の概念について説法したはずなのだ。しかし理趣経では、釈迦ではなく、大日如来が説法をする。なぜかというと、そうすることによって、釈迦という個人を超えた普遍の真理を表現できるからだ。突き詰めて考えると、真理は釈迦が生まれる前から「常駐」していたはずで、釈迦がその真理を発見した、ということになる。すると、いっそのこと、釈迦より大日如来に説法をしてもらったほうが、より説法の普遍性が際だつ、というわけだ。
こういうと、えらく高級な話をしているように聞こえるかもしれないが、この考え方はエンターテイメントの世界ではごく普通のことだ。たとえば『スターウォーズ』には、悪の象徴のダースベイダーや、生を育むプラスの象徴であるフォースの騎士が登場する。これらは本来、人の心に棲む様々な属性を極端に表したものであり、人そのものではない。考えてみればあんなに極端な人はそういない。しかし、属性を体現したキャラクターたちのドラマを描くことによって、日常生活では見えにくい真実を物語の中に閉じこめることができる。しかし、タレントなどリアルな人に心の属性について語ってもらっても、その人の人気がなくなった途端、内容まで忘れ去られてしまうだろう。それは、宗教のように、何千年も伝わるものではないし、一部の作品のように何百年ももつものではない。つまり実在の人物に限定すると、ものごとには普遍性がなくなってしまうのだ。仏教の考え方は、決して日常から遠いものではなく、普段楽しんでいる映画や小説などにも現れているといえる。
新興宗教は、普遍化した真理というより、教祖の観相した世界が中心となっている。教祖は自分自身の霊能で観たことを、確信をもって語っている。借り物の知識ではなく、自分でこうと感じたものを語るのはよい部分もあるかもしれない。しかし、これでは「あの教祖様はすごい」という具合に、内容より「人」が先に立ってしまう。すると教祖の「我」が出てくるのも致し方ない。ヒーラー、チャネラーの人たちも、同じことがいえるような気がする。わたしが『理趣経』を読んで思ったことは、近代のスピリチュアル・ムーブメントは、何千年も積み重ねて普遍化されてきた仏教とはずいぶん違うのだな、ということだ。